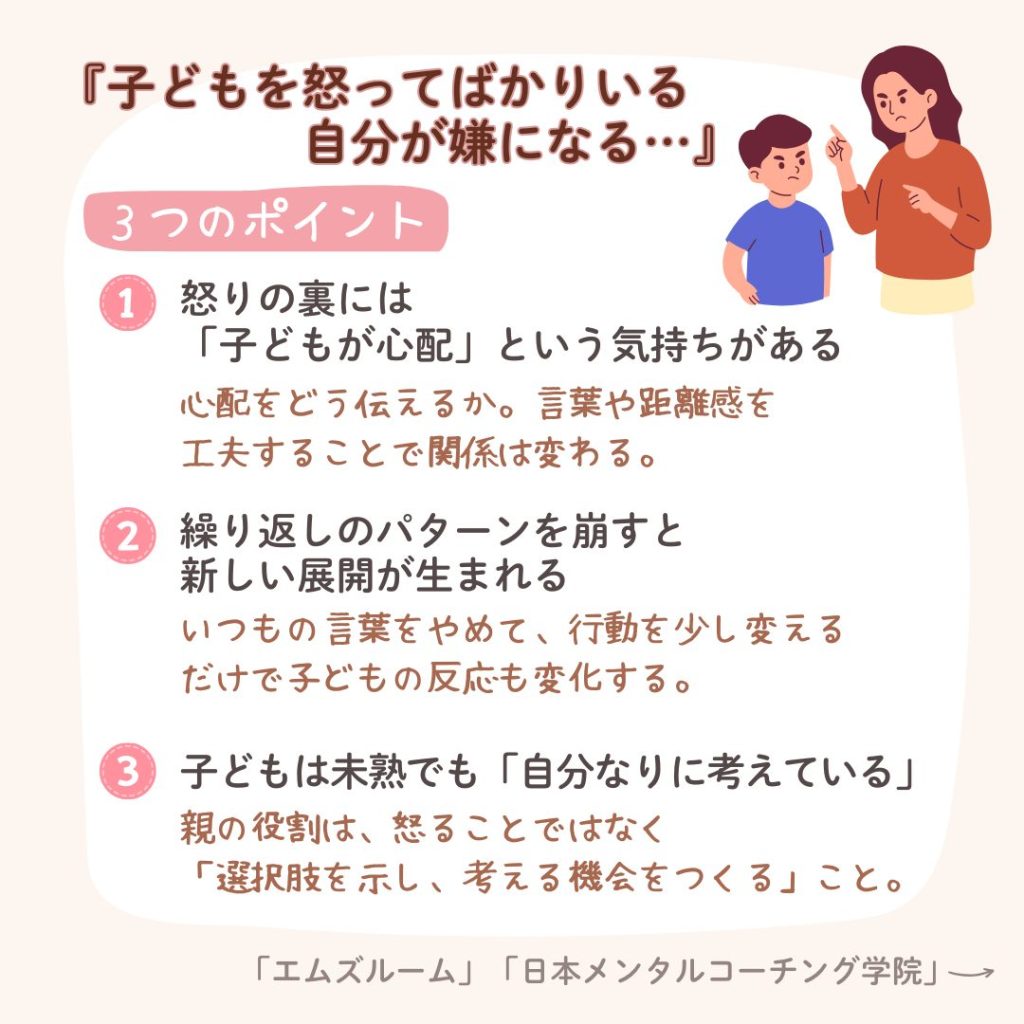「怒りたくないのに、つい怒ってしまう」
子育てをしていると、そんな場面は誰にでもあります。
「私が怒らなければ家の空気は悪くならない」
「でも私が怒らないと、子どもはだらだら遊んでばかりでダメになる」
そんな焦りから、
「早くしなさい」
「なんでやらないの」
と繰り返してしまう…。
けれど、怒りは体力を使いますし、怒った後は気持ちが沈んでしまうものですよね。

怒りの裏にある「子どもが心配」という気持ち
多くの親は、子どもが大きな苦労をせずに成長できるようにと願っています。
ご自身の経験や、周囲を見てきたからこそ「このままでは困る」と気づけるのです。
だからこそ、子どもの行動が気になります。
-
朝なかなか起きてこない
-
忘れ物が多い
-
夜更かしをする
-
お菓子ばかり食べる
-
お風呂に入らない/長風呂をする
挙げればきりがないほど心配のタネがありますよね。
でも、優しく伝えても聞いてくれない。
そのうち声が荒くなり、大きな声で繰り返してしまう…。
その根っこにあるのは、すべて「子どもが心配だから」。
しかし、口うるさく言えば言うほど、子どもは自分で考えるのをやめてしまいます。
人間は、自分で考えて行動し、成功や失敗を重ねることでしか、自分をコントロールする力は育たないのです。
怒りの裏にある「繰り返しのパターン」
思い出してみてください。
よくケンカする相手とのやり取りは、毎回同じような言葉の応酬になっていませんか?
人間関係には「こう言われたら、こう返す」という無意識のパターンがあります。
子どもとのやり取りも同じです。
だからこそ、
親が「いつもと違う行動」を取れば、子どもの反応も変わる可能性があるのです。
子どもも「自分なりに考えている」
忘れてはいけない大切な視点があります。
-
子どもも、自分なりに考えている
-
子どもも、自分の人生を良くしたいと思っている
ただし、人生経験が浅いため、方法は未熟です。
好奇心が強く、「正しいこと」より「やりたいこと」が優先されることもあります。
それでも「遊んでばかりではいけない」という理解は、子どもなりに持っているのです。
親の役割は、
-
子どもが持っていない選択肢を教える
-
工夫の仕方を伝える
-
自分で考える機会を与える
ことではないでしょうか。
まずは「観察」してみよう
例えば、
-
ここでいつもなら注意するけど、あえて見守ってみよう
-
どうしても必要なら「何やるんだっけ?」と軽く声をかけてみよう
そんな風に行動を少し変えるだけで、子どもを新しい目で観察することができます。
もちろん、すぐに理想の姿に変わるわけではありません。
でも、一週間、一か月と続けるうちに、子どもとの関係性は少しずつ変わっていくはずです。
それでも「怒らないと何もしない」と感じる方へ
「うちの子は、私が怒らないと本当に何もしないんです」
そんな風に感じる方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、ぜひ エムズルームの初回相談 にお越しください。
お子様の状況を丁寧にお聞きし、「その子に合ったアプローチ」を一緒に見つけていきます。